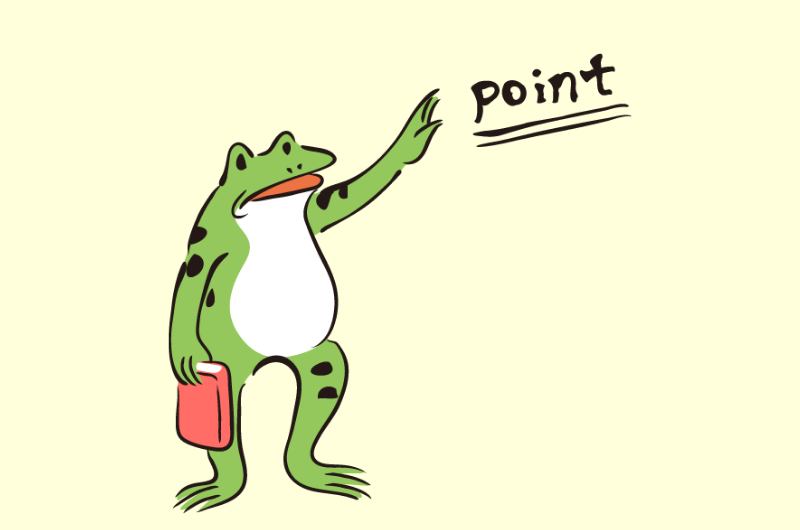福祉の仕事の中で、記録は業務上必要なスキルであり、また記録そのものが利用者への支援となります。
支援の実践過程を記した記録は、利用者支援を示す根拠であり、希望や要望を引き出し、その経過から達成度を確認したり、実践を振り返るための拠り所となります。
記録の意義、意味や目的を理解して、実践につながる記録のあり方を整理します。
愚痴から始まる記録の学び
再び愚痴です。
なので愚痴歓迎でない方はこの項をぜひ読み飛ばしてください。
以前勤務していた就労移行支援事業所では、記録についても指示指導が何もありませんでした。
記録の内容についても、書き方についても、方針や趣旨が何もない。
監査対策のための記録しか残しておらず、「文字が書いてあり体裁が整っていれば内容はどうでもいい」くらいの姿勢でした。
福祉業界で初めて就職した事業所がそんなだったので、「え?福祉事業所の記録ってそんなもの?」と疑念を抱きつつ、しばらくの間は事業所のあり方に合わせて働いていましたが、やはり誤った姿勢であったことが後日わかって安堵したものです。
前の事業所を退職する数か月前になって「本来記録はこういうものではない」と、コンサル的な立場の人から指摘を受けました。でも「こうあるべき」ということは尋ねても教えてもらえず、指示指導はないまま。結局どうすればいいのかよくわからないままでした。
否定だけされてもねぇ・・。
ご指摘いただけたのはありがたかったけれども、結局その人も、記録のあるべき姿について感覚でわかっているだけで、言語化するところまではできていなかったのでしょう。
今の勤務先では、記録こそ支援の証。
記録がちゃんと書けないと一人前に仕事をしたとは言えないので、福祉業界3年目にして、改めてというか初めて、きちんと学びます。
主観的なことと客観的なこと
主観的理解と共同主観的理解
主観的なこと
- 利用者の主観的・個人的世界を理解しようとすること。主観だけで利用者を理解しようとすると、問題解決の方法が大きく変わってしまう。
- 利用者の日常生活における主観的理解を認識し、利用者の希望・要望や生活の支障を聴き取ること。
- すぐに本音を言えない人には、根気強く関わり、生活の主体は利用者だと思えるように関わる。
客観的なこと
- 客観的なことには、利用者の身体的状況、医療的状況、経済的状況、環境的状況など、数字で表されるデータに関連したことも多く含まれる。
- データの捉え方には個人差があり、支援の種類や程度がデータでのみ決まるものではないが、データは利用者の生活の困難や障害による支援の必要性を明確にする。
- 障害があるという事実のみに捉われず、障害を抱えてどのように生活しているか、その生活障害を当事者はどのように捉えているか、当事者の日常生活や社会生活上の問題はどのようなことなのか、多方面から真のニーズを模索することが大切。
記録における主観と客観
支援者は客観的な事柄をもとに、専門性を持って、主観的に記録する。
客観的に書こうとすると事実の羅列になる。
事実の背景を憶測すると主観的になりがち。
事実に対する利用者の認識、「利用者はどのように現実を捉えているか」を、専門職者として常に意識して、利用者の主観的・客観的事象も大事にしたい。
利用者の経済観・生活観といった主観的な捉え方と、利用者の望む生活像(目標)を意識して記録する必要がある。
利用者が何を望んでいるか、援助が利用者の主体性を尊重したものであるか、ということを記録に残し、その達成度の期間を定め、確認・検討しなくてはならない。
(つづく)