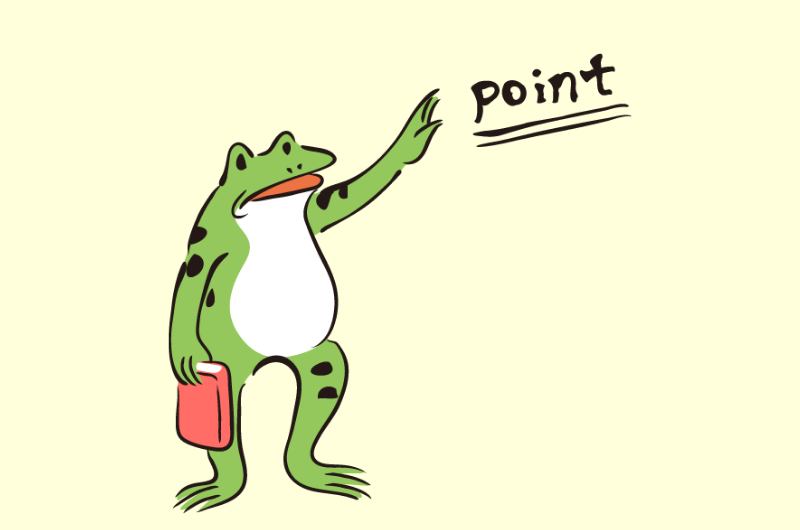こんにちは、ブジカエルです。
2019年より就労移行支援事業所で支援員として勤務し、福祉の仕事の素晴らしさにすっかり感化されました。福祉についてもっと理解したいし、支援の幅を広げたく、社会福祉士の資格を取得することにしました。
その学習の記録です。
今回は、40代半ばにして社会福祉士の資格を取得するための勉強方法についてまとめました。
できれば1発合格を目指します。
前提:働きながら、独習で学ぶ
働くことをやめて、勉強にだけ集中するのというのは考えませんでした。
仕事を辞めて余裕ができると他の余分なことを始めてしまいそうな気がするし(マルチ・ポテンシャライトだから)、試験に合格した頃の景気によっては再就職が難しくなるかもしれないのでリスキーだと思いました。
なので、1年半かけて専門学校の通信課程で受験資格を得つつ、約2年後の合格を目指します。
学校から課される課題だけやっていても合格するわけがないので、試験対策の勉強は独習で進めていきます。良い参考書は既に豊富にあるので、ユーキャン等のさらなる通信講座は使いません。
社会福祉士試験の合格基準
上記サイトに掲載されている基準は以下2点。
- 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。
- 18科目すべてにおいて得点があった者。
出題形式は、五肢択一を基本とする多肢選択形式で150問。
試験時間は240分。
- 96秒(約1分30秒)で1問解き、
- 約90問程度以上正解し(都度補正あり)、
- 18科目中、1科目たりとも0点にならない
をクリアすると。
なるほど・・
試験に出る範囲がとても広いので、なかなかハードなような気もします。
勉強にかける時間
社会福祉士の勉強方法について書いてある記事を20ほど見てみたところ、200~300時間としているものがほとんどでした。
言い出しっぺがどこかにいて、他の人はそれを引用したのかな?とも思うのですが・・
300時間て、授業を受けたり、テキストを読んだりする時間も含むんですかね?
記事を読んだだけではよくわかりませんでした。
1日1時間でいいのであれば、1年未満で受かる計算ですが、要点をまとめた参考書を読むだけでも結構時間がかかるのに、それを覚えて、過去問を解いてその問題をきちんと理解するところまで、1年で到達するだろうか?
疑問です。
毎日2時間、2年間勉強したら、2×365×2=1460時間 なので、余裕で受かるかも?
2時間×週5日で勉強したとしても、2年間で1042時間になるので、やっぱり余裕で受かるかも。
勉強方法のポイント
さて、ここからは社会福祉士試験に合格するのための勉強方法のポイントをまとめます。
今まで見聞きしたこと、自分で色々試してきたこと等、色々含めて整理しました。
例えば、国家資格キャリアコンサルタントは一発で合格したし、放送大学・大学院では何十科目もの単位認定試験を受けてきましたが、一度も落としたことがありません。健康管理士や食生活アドバイザー等の民間資格も全て一発で合格してきました。
働きながらこれだけの成果を出してきたのは、意識的&無意識に、それなりにポイントを押さえた勉強法を実践してきたのだろうと思います。
今回はその、私が無意識に押さえていたポイントも言語化しました。
なお、この記事を書くにあたって、社会福祉士試験に合格した人たちの勉強法を色々と教えていただきましたが、「最低限の時間しかかけない」「とにかく効率」「最短で」「受かりさえすればいいから」みたいな勉強の仕方は参考にしませんでした。
私の目指すところとは方向が異なるので。
なので以下の内容は、「資格がとれさえすればいい」という人にはあまり向かないかもしれません。
毎日勉強&復習を適宜行う
勉強した内容を長期記憶として脳にとどめるには、2週間で3回ほど繰り返す必要があります。
理想は、暗記すべきことは3日連続で反復し、1カ月後に再度見直すという方法。
そのため、少しの時間でもいい、復習だけでもいいので、できるだけ毎日勉強することが望ましいと考えられます。
時間を決めて勉強する
働きながら勉強するので、意識して勉強するための時間を確保する必要があります。
朝は理解する勉強、夜は記憶のための勉強
脳は朝が最もクリア。
難しいことを理解する勉強や、レポートを書くのは朝に行います。
夜は覚えるための勉強。
海馬はその日入力された情報を、睡眠中に整理して保存します。暗記した後にすぐ眠ると、より記憶として定着しやすくなるそうです。
全体を俯瞰しながら勉強を進める
脳の力をより引き出すために、脳にストレスをできるだけかけないようにしたい。
学習内容の全体像を俯瞰し、どこまで学んだのかを把握しながら学習を進めることで、脳はストレスを感じにくくなります。
暗記型ではなく論理型で
私は暗記型の勉強が好きではありません。
暗記が得意ではないからかもしれません。
という理由だけではなく、社会福祉士養成課程の試験対策の先生が、試験対策は「暗記型ではなく論理型で」と言っていました。
暗記型だと、資格は取ったもののそのために勉強した内容は忘れてしまった、となりかねない。年齢、時間、今後の積み重ね等様々なことを考慮したら、丸暗記ではなくちゃんと理解するための勉強をするのがいいよ。という理屈。
資格取得のために勉強するというよりは、知りたい理解したいことがあるから資格取得を利用して勉強しているので、先生の言う通り、論理型でいこうと思います。
試験合格、資格取得だけが目的の人は、暗記型の勉強をすればよく、テキストを読む必要はないのでしょうが、(私には暗記型の勉強というのが非常に無駄な行為のように思えますが)、私は社会福祉そのものを根本から理解し学びを進めたいので、恐らくテキストはしっかり読むことになります。
もっとも、論理型でいくとはいえ、理論に関してはどうしても暗記の要素が入ってきてしまいます。そこは辛抱、暗記しろ自分。
過去問をしゃぶりつくす
専門学校の試験対策の先生が、過去問をしゃぶりつくせと言っていました。
社会福祉士という資格を得るに値するかどうかを判断する試験問題は、社会福祉の専門家たちが相当に手間と時間をかけて作り検討に検討を重ね練り上げた問題であり、しゃぶりつくす価値があるそうです。
問題集はたくさん出ているけれども、半端な問題集を何冊も解くより、過去問をしゃぶりつくせとのことでした。
毎年7~8月頃に、前回の試験の傾向をおさえ、法改正にも対応した新しい参考書や問題集が発売されるそうなので、試験の半年前くらいになったらそのあたりも勉強すると良いかも。
勉強する場所は自宅、自分の縄張り内
カフェや図書館に行かないと、という人もいますが、人の体は本能的に変化を嫌います。常に同じ状態であろうとする性質があるため、いざ勉強を始めようとするとおっくうに感じてしまいがち。
なので、自分の家で、いつもの場所で勉強することで、勉強を始めることへの心理的ハードルを下げます。
1日30分の有酸素運動
脳の働きを良くするには、運動も重要。
記憶力コンテスト優勝の常連さんたちが、トレーニングのかなりの部分を有酸素運動にあてていると言っていました。
暗記型の試験対策ではないとはいえ、諸種理論や歴史的なことに関してはどうしても暗記の要素が必要なので、有酸素運動も必要でしょう。
海馬の神経細胞を発達させるたんぱく質「BDNF(脳由来神経栄養因子)」は運動で増えるそうで、BDNFを増やすには30分程度の軽い有酸素運動が効果的とのこと。
おわりに
試験当日までの勉強のし方は、漠然とは描いていたのですが、文字にすることでしっかり整理できました。
これで、明日以降の行動計画が立てやすくなりました。
これから何らかの試験等を目指して勉強する方にとっても参考となれば幸いです。
この記事を書きながら思い出したのですが、以前、地元の大手社会福祉法人でご活躍中の社会福祉士の方が「毎日仕事を終えて家に帰ってから教科書を少しでも読むことができればきっと受かりますよ」と言っていました。
その方も働きながら取得した人で、特に暗記が得意とか頭がすごくいいとかいうタイプではなく(失礼!好意です。穏やかで優しくて、とても素敵な方なんです。)、特に難しい試験ではなく地道な努力が実を結ぶ試験だよ、ということなのでした。