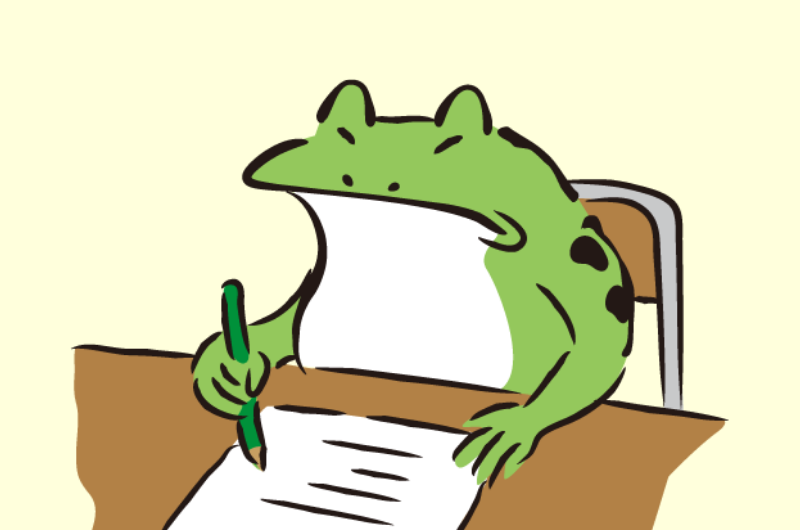この記事は、社会福祉士養成課程(通信)の28番目のレポート(科目は「人体の構造と機能及び疾病」)に関することをまとめたものです。
A評価を得たレポートの実例つきです。
お忙しいでしょうから、ぜひ必要な個所に絞って見てくださいね。
以下の記事にまとめた手順に沿ってレポートを作成する準備を進めました。


レポートは2択
レポートの課題は、以下の2つから選べました。
(a)感染症について、感染経路別に分類し、感染対策を念頭に置きながら論じなさい。
(b)認知症の代表的病型およびそれぞれの特徴を論じなさい。
感染症と認知症のどちらにも関心はあるのですが、今回は(b)にしました。
レポート作成の手順
毎度恒例、「社会福祉士養成通信課程で提出するレポートとその作成方法について【土台=基礎編】」の「レポート作成の手順」に沿って作業を行っていきます。
テーマ分析
「認知症の代表的病型およびそれぞれの特徴を論じ」るというテーマが、どのような内容を期待して設定されたのかを考えます。
また、社会福祉士養成通信課程におけるレポートは、
- 学習を進めているよ!ということを学校に知らせる
- こんなふうに理解しているよ!ということを先生に知らせる
ということも目的としていると考えられるため(参考:社会福祉士養成通信課程で提出するレポートの意味)テキストの内容を踏まえつつ、少し発展させたレベル内容も盛り込めるとベターかと思います。
今回のレポートは、
- 認知症の代表的病型とそれぞれの特徴
- 上記に関する考察
以上2点が端的にしっかり書けていれば(=本質的なところが押さえてあれば)、及第点はもらえるでしょう。
材料を集める
レポートを書くにあたって必要な材料を集めます。
学校指定のテキストの中や、テキストに出てきた資料から主に材料を探します。
材料を集める
参考
認知症とは
1.「認知症」ってどんな病気?
記憶や判断力の障害により、生活に支障をきたす状態「認知症」とは老いにともなう病気の一つです。さまざまな原因で脳の細胞が死ぬ、または働きが悪くなることによって、記憶・判断力の障害などが起こり、意識障害はないものの社会生活や対人関係に支障が出ている状態(およそ6か月以上継続)をいいます。
認知症の代表的なもの
● アルツハイマー型認知症
最も多いパターン。記憶障害(もの忘れ)から始まる場合が多く、他の主な症状としては、段取りが立てられない、気候に合った服が選べない、薬の管理ができないなど。● 脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血、脳動脈硬化などによって、一部の神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、神経細胞が死んだり神経のネットワークが壊れたりする。記憶障害や言語障害などが現れやすく、アルツハイマー型と比べて早いうちから歩行障害も出やすい。● レビー小体型認知症
幻視や筋肉のこわばり(パーキンソン症状)などを伴う。● 前頭側頭型認知症
会話中に突然立ち去る、万引きをする、同じ行為を繰り返すなど性格変化と社交性の欠如が現れやすい。なお、遺伝によるケースは稀であり、さらに働き盛りの世代でも発症するおそれもあることから、認知症は誰にでも起こりうる病気と言えます。
材料を端的に挙げればこんなところ。
これを1200文字前後に膨らませてレポートとします。
A評価のレポート例
 ブジカエル
ブジカエルご参考になれば幸いです。
完全コピペはダメですよ。
掲載するレポートの評価は以下の通りです。
点数 80点
総合評価 A
項目別評価では、
・課題の理解度 B
・論旨と構成 A
・自己の見解 A
以下、レポートです。
認知症は、一旦発達した脳機能が後天的な器質性障害によって低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態である。認知症の代表型としては4つ挙げられ、患者数が多く病因がはっきりしている「アルツハイマー型」「レビー小体型」「血管性」「前頭側頭型」が4大認知症とされている。
1. アルツハイマー型(AD)
日本国内の認知症患者のうち全体の60〜70%を占めており、最も多い。脳の中に特殊なタンパク質のかたまりが増え、脳の正常な神経細胞がゆっくりと減少していく「神経変性」である。記憶障害から始まる場合が多く、記憶の中でも近時記憶の障害が最も顕著にかつ初期から見られる。症状は緩やかに進行し、見当識障害や実行機能障害が起こり、物盗られ妄想も発現する。その他主な症状としては、段取りが立てられない、気候に合った服が選べない、薬の管理ができない等がある。
2. レビー小体型
70代以降に見られることが多い認知症で、脳の様々な部位にタンパク質のかたまりであるレビー小体ができることで発症する。記憶障害はADと比べて軽い傾向で、最も特徴的な症状は「ないものが見える」「影や衣服がほかの物や人に見える」といった幻視であり、幻視に伴った妄想が生じる場合もある。パーキンソン病のような症状や、意識のレベルが著しく変化したり、睡眠中に夢を見て声を出す、夢の内容と同じ行動をとる症状(レム睡眠行動異常)が出ることもある。便秘や急に起きたときの血圧低下などの症状も多く見られる。抑うつ傾向も見られるため、初期にはうつ病と勘違いされやすい。
3. 血管性
脳卒中や心停止等による脳損傷や脳の血管炎などが原因で起こり、60歳以上の男性に多く見られる。脳梗塞などの発作を機に発症するが、気づかない程度の小さな発作の積み重ねによって発症する場合も多い。脳の損傷部位により障害される機能が異なるため症状は千差万別だが、脳の前頭葉白質が障害されるケースが多く、その場合は記憶障害よりも遂行機能障害や精神運動の遅延、意欲の低下が目立つ場合が多い。感情面での変化も特徴的で、感情失禁や抑うつ状態になったりする。歩行障害を中心としたパーキンソン症状が合併する場合もある。
4. 前頭側頭型
脳の前頭部と側頭部の脳細胞が徐々に失われることで発症する。当該部位における萎縮や血流低下が特徴的である。症状は行動障害、言語や運動の機能障害等様々で、認知能力や人格、そして最終的には自立性が徐々に失われていく。初期に空間的能力や記憶が比較的良好に保たれる点がADと異なる。
誰もが必ず年をとる。そして、65歳以上高齢者のうち認知症高齢者は増加していくと推計されている。高齢者支援に直接携わる場合はもちろん、業務が別領域だとしても、認知症を含む加齢に伴う変化や症状に関する理解や知識を一般的かつ個別的にも広げ、深め、さらに最新の情報に更新していくことは必須だろう。そのようにして、誰が認知症を発症しても初期段階で適切な支援につなげられる、また認知症がある人も同じ社会でともに生きる社会に貢献できる支援者でありたい。
先生からのコメントとしては、
・アルツハイマーでは薬物療法に言及するとよかった
・正常圧水頭症、プリオン病などについても触れるとよかった
といったことが書かれていました。